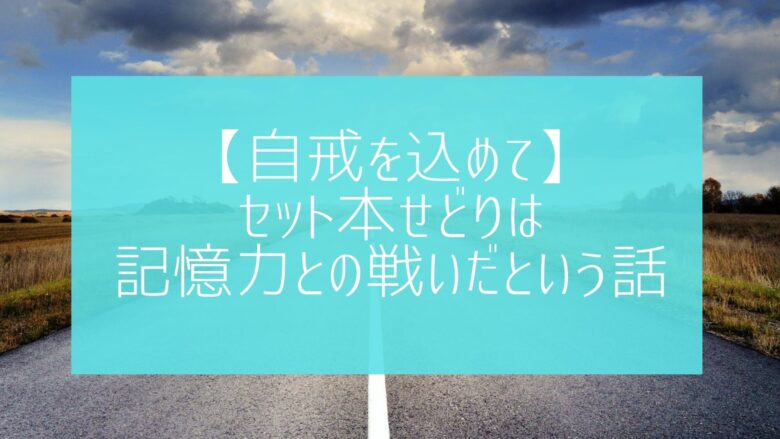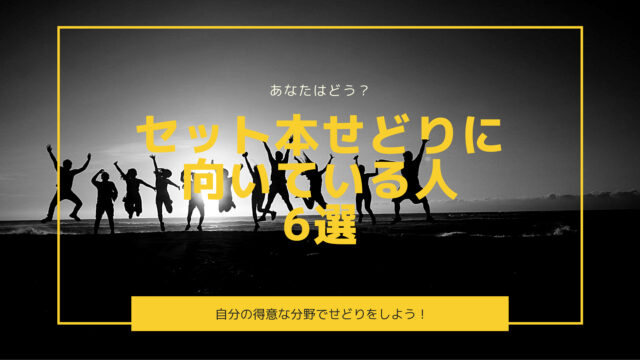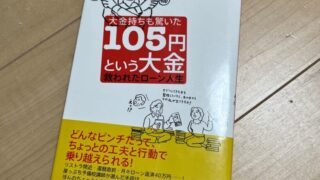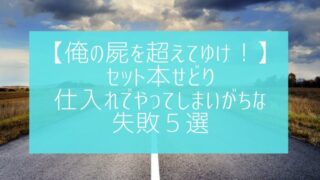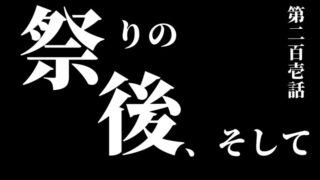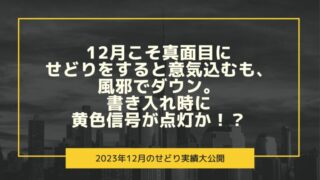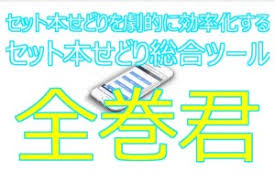こんにちは!イチローです(^^)
12月に入って、やはり売れ行きが上がって来ていますね。
Twitterを見ていても多くの本せどらー、セット本せどらーがそう
仰っているので間違いないでしょう。
また、ベースが上がっていることに加えて、あちこちでトレンドが発生し
お祭り状態です。
1年で最も活況な時期ですので、思う存分堪能したいものです😄
ただ、『ちょっと待ってください』と言いたいのです。
そんなにあちこち手を広げて大丈夫なのかと、問いたい。
これは自分自身への戒めです(苦笑)
セット本せどりはリスト勝負で、どれだけ商品知識があるかが、
収益の多寡を決める重要な要素であります。
うんうん、それは間違いない。
たしかに単行本などと比べると覚えるべき商品リストは
圧倒的に少ないですからね。
でも、一度覚えた商品リストも実践レベルで維持継続することは
意外と難しいものです。
今日はセット本せどらーが陥りがちな『記憶力』にまつわる
落とし穴について解説します。
トレンド情報を詰め込み過ぎて、定番商品忘れがち

トレンド情報や新たな利益商品情報を集めまくっていると
元々知っていて手堅く利益が取れていた商品を忘れがちになります。
キラキラした商品情報に目を奪われている状態ですね。
例えば、1500円仕入れ⇒4000円売り、なんて地味じゃないですか。
この価格帯なら、店舗を回っていれば自然と集まるというレベルの
商品はゴロゴロあります。
でも、華がないんです。
すると価格の自然なアップダウンなどにより、たまたま利幅が薄いことが
あったり、たまたま店舗で見かけないことが続いたりすると、そのうち頭から
消えて行ってしまうのです。
その商品のことを忘れた訳ではありません。
意識がトレンド商品ばかりに行ってしまい、定番のいつも取っている商品の
ことを忘れてしまうんです。
実際に店舗で棚の前に立った時に、その商品へ手が伸びなくなるのです。
不思議ですよね。
本来なら定番商品をしっかりと固めて、トレンドでプラスアルファを
取るという方法が手堅いのですが…
こういう状態になってくると売り上げが頭打ちになるのではないかと
思います。
時間の限られている副業勢であれば、なおさら、いかに定番商品でも
しっかりリサーチして、取りこぼしを最小限にすることに力を注ぐべきでしょう。
未コンプ在庫が増え過ぎて、集めていたセット忘れがち
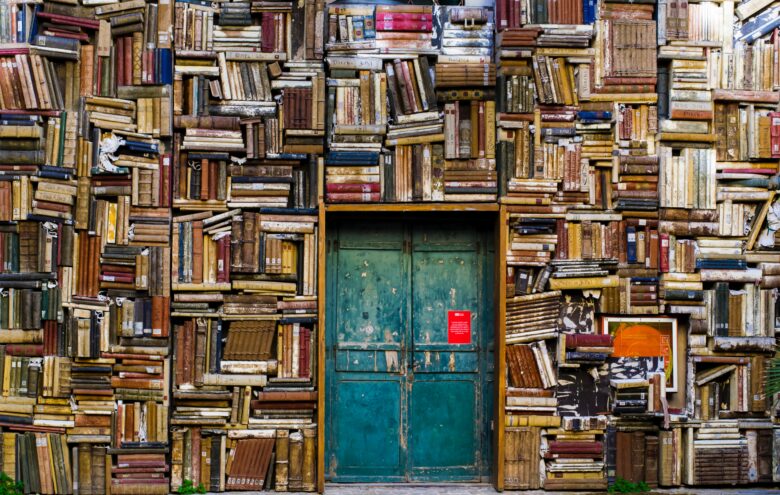
セット本せどりで、ある程度売り上げのボリュームを出していこうと
思えば、バラで買い進めてコンプするということが欠かせません。
そういった中には、コンプまで数か月掛かるものも出てきます。
そうなってくると、集めていることを忘れてしまうのです。
本当に自分でもバカだなと思います。
一番危ないのは、コンプまで5冊くらいの時でしょうか(笑)
流石にコンプまで1,2冊となってくると緊張感も戻って来て
その商品に手が伸びるようになってきます。
集めていることを忘れると、店舗にその商品があっても目が行かずに
スルーしてしまって、コンプが更に遠のきます。
こういったことを防ぐには、
- 家の在庫棚を整理すること
- 仕入れに出かける前に家の棚をしっかり見ること
ということをすれば、かなり緩和されると思います。
どんどん出品数を増やしている時期こそ気を付けたいものです。
商品知識を増やす努力をせず、セット本せどりは『もうダメかも』と思いがち

これは、初心者を脱したくらいのせどらーに当てはまると思います。
先に説明した内容と矛盾するかもしれませんが、
長く売り上げに貢献してくれた商品でも、時間の経過とともに
自分の仕入れ基準を下回ってしまうことも出てきます。
なので、自分の商品知識を常にフレッシュな状態を保つために、
新陳代謝が必要です。
でも人間『これで一人前になれた』と思うレベルまで行くと、
そこから更に努力すること、または、それまでの努力を継続することが
難しくなってきます。
調子に乗っちゃってる状態とでも言うのでしょうか…💦
知識がリフレッシュされないと、自分の頭の中の商品リストは
徐々にですが確実に古ぼけていくのです。
商品リストが古ぼけていくと、そこから得られる収益の結果も
推して知るべしってところでしょう。
どのせどり手法でもそうでしょうが、その手法で輝き続けようと思えば、
自分の記憶の中の商品リストを常に更新する必要があるのです。
まとめ
今回は記憶力という括りで、セット本のことを見てみました。
今回挙げさせてもらったのは、すべて私自身への戒めでもあります。
『これで大丈夫』
と思った瞬間に、消長の激しいせどり業界においては
退場へ向けたカウントダウンが始まるというくらいの
気持ちでいた方が良いでしょう。
私も年々低下する記憶力と戦っていきたいと思います😁
また、それを支えるモチベーションの維持も重要ですよ。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
それではまた!
分からないことや、疑問に思ったことがあれば問い合わせフォームか
TwitterのDMから質問、メッセージをお待ちしています(^^)